秋が深まり、気温の変化が大きくなると体調を崩しやすくなります。特に60歳を過ぎると、若いころのような回復力は落ちてきて「ちょっと寒気がする」「喉がイガイガする」といった小さな不調から、すぐに風邪に発展してしまうことがあります。
そんなときに役立つのが、昔から受け継がれてきた 家庭の知恵 です。薬やサプリメントに頼る前に、自然の力を上手に使うことで、体を温め、免疫を整えることができます。
今回は特に有名な「大根はちみつ」と「しょうが湯」を中心に、60歳以降の女性にも取り入れやすい昔ながらの風邪予防法を詳しくご紹介します。
大根はちみつの知恵
大根の栄養と効果
大根は冬野菜の代表。消化を助ける酵素 ジアスターゼ をはじめ、ビタミンC、食物繊維が豊富に含まれています。特に「喉の炎症を和らげる」「咳を落ち着かせる」作用が知られており、昔から「風邪をひいたら大根」と言われるほどです。
大根の辛味成分 イソチオシアネート は抗菌作用があるため、風邪の原因となるウイルスや細菌に対抗する自然の力を持っています。
はちみつのパワー
はちみつは古代エジプト時代から薬として使われてきた食材。殺菌効果・抗酸化作用に加え、喉を潤す働きがあります。乾燥する秋冬にピッタリで、喉の痛みや声枯れを防いでくれるのです。
さらに、自然な甘さで飲みやすく、心もリラックスできるのが魅力です。
作り方と飲み方
大根をよく洗い、皮付きのまま1cm角に切る。
清潔なガラス瓶に入れ、ひたひたになるまで蜂蜜を注ぐ。
常温で2〜3時間ほど置くと、大根から水分が出て透明なシロップができる。
このシロップをスプーン1杯なめる、またはぬるま湯に溶かして飲むと喉にやさしいです。冷蔵庫で3日ほど保存可能。
私自身も子どもの頃、咳が出ると母が必ず「大根はちみつ」を作ってくれました。薬が苦手でも、甘くて美味しいので喜んで飲んだ思い出があります。今でも喉がイガイガすると懐かしい気持ちで作ります。
しょうが湯の知恵
しょうがの温め効果
しょうがは、冷え性や風邪予防に欠かせない食材。東洋医学でも「体を温める食べ物」として古くから重宝されてきました。
しょうがに含まれる成分 ジンゲロール は体を温める効果があり、加熱することで ショウガオール に変化するとさらに血行促進作用が高まります。体の芯から温まり、発汗を促して体温を調整してくれるのです。
簡単なしょうが湯の作り方
しょうがをすりおろし、小さじ1杯ほどをカップに入れる。
熱湯を注ぎ、はちみつを大さじ1加える。
レモン汁を少し入れると爽やかで飲みやすい。
体がポカポカしてきて「風邪をひきそう」と思った時に飲むと効果的です。私は夜寝る前に飲むことが多いのですが、布団に入るころには体がじんわり温まり、眠りも深くなるのを感じます。
アレンジ方法
黒糖を加えるとさらにコクが出て栄養価もアップ。
シナモンをひとふりすると体を温める作用が増し、香りも楽しめる。
牛乳にしょうがとはちみつを加えて「しょうがミルク」にすると飲みやすく、体も芯から温まります。
スポンサードリンク
その他の昔ながらの風邪予防法
梅干し
梅干しは殺菌作用のあるクエン酸を多く含みます。お湯に梅干しを入れた「梅湯」は、体を温めながら疲労回復を助けてくれます。

ネギ
「風邪をひいたらネギを首に巻け」という言葉も有名です。ネギの成分 硫化アリル には殺菌効果や血流を良くする働きがあり、実際にネギを食べるだけでも風邪予防になります。ネギたっぷりの味噌汁は体も温まり、栄養も取れる一石二鳥です。
葛湯(くずゆ)
葛粉をお湯で溶いた葛湯は、風邪をひいたときの定番。体を温めると同時に、胃腸にやさしく食欲がないときにも安心です。ほんのり甘いので心もほぐれます。
取り入れるときの注意点
はちみつ は1歳未満の子どもには与えてはいけません。
しょうが は胃腸が弱い人には刺激になる場合があるため、少量から試す。
梅干しやネギ は塩分が多いため、高血圧の方は食べすぎに注意。
昔ながらの知恵は「薬ではない」ので安心して取り入れられますが、自分の体調や体質に合わせて工夫することが大切です。
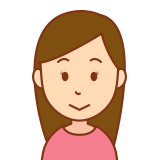
昔ながらの風邪予防法には、大根やしょうがといった身近な食材が活用されています。これらはどれもスーパーで手に入り、特別な手間もかかりません。
現代は薬やサプリメントに頼ることもできますが、自然の力を借りて体を守る方法を知っておくと安心です。大根はちみつで喉を潤し、しょうが湯で体を温め、梅干しやネギで免疫を整える。そんな暮らしの知恵を、これからの季節にぜひ役立ててみてください。
昔ながらの知恵は「おばあちゃんの知恵袋」とも呼ばれますが、その知恵は今もなお私たちの健康を支えてくれます。薬に頼る前に、まずは台所の食材を思い出してみましょう。
スポンサードリンク


